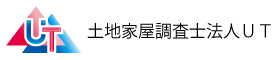-
土地家屋調査士と測量士
土地の広さや形状などの現況を調べる「測量」は、土地家屋調査士の業務のひとつとして挙げられます。しかし、「測量業務を手がける人」と言えば、土地家屋調査士だけではなく測量士も有名です。この両者には、どんな違いがあるのでしょうか。
土地家屋調査士の測量は「登記向け」
土地家屋調査士が手がける測量は、「登記をするための測量」です。建物の新築や土地の売買、境界位置の確定、土地を2つに分ける、農地を宅地として利用する、など、土地の用途や境界を明確にするという趣旨の登記が必要となった場合が、土地家屋調査士の出番となります。
測量士の測量では登記できない
土地家屋調査士が「登記をするための測量」を手がけるのに対して、測量士は、登記に関わる測量をすることができません。そのかわり、トンネル工事や道路工事・ダム工事・橋を架ける工事など、公共系の工事をするための測量を手がけることができます。逆に、土地家屋調査士は、こうした公共系工事のような、「登記を目的としない測量」を取り扱うことはできません。つまり、測量という枠の中でも、土地家屋調査士と測量士の分野にははっきりとした棲み分けがなされており、お互いの担当領域には踏み込めない決まりとなっているのです。
資格を管轄している省にも違いがある
土地家屋調査士と測量士は、どちらも国家資格。「測量の国家資格」という点だけを見ると同じように見えますが、実は資格を管轄している省にも違いがあります。土地家屋調査士の管轄は法務省ですが、測量士の管轄は国土交通省となっています。「不動産登記を担当しているのが法務省法務局であり、公共事業を担当しているのが国土交通省である」ということを考えれば、両者の測量の分野に明確な違いがあるのも当然と言えます。
個人向けの測量ができるのは土地家屋調査士
というわけで、土地家屋調査士と測量士、この両者の測量の分野には大きな違いがあります。個人が測量依頼を必要とする場合、その理由は登記目的であることがほとんどですから、個人が測量を依頼する場合は、基本的には土地家屋調査士に依頼するのが正解と言えるでしょう。
ただ、例外として「登記をしてもらう必要はない、単に土地面積等を測ってもらいたいだけ」などという場合は、個人が測量士に依頼するケースもあります。しかし、その結果「やはり登記をしたい」となっても、測量士には、その先の手出しはできないという点は理解しておく必要があります。測量士の本業は、官公庁や地方自治体などが依頼する公共事業に関する測量なのです。
-
表題登記(表示登記)とは何か
表題登記(表示登記)とは「まだ登記されていない土地や建物に対して、はじめての登記を、登記簿の表題部(登記簿の1ページ目)に作成すること」を指します。具体的には、埋め立て・造成などで新しくできた土地や、更地に建物を建てる時などに、この表題登記を行います。
表題登記と表示登記の違い
表題登記は、かつては表示登記と呼ばれていましたが、平成16年6月18日公布・平成17年3月7日施行の不動産登記法改正の際に、表示登記から表題登記へと名称が変わりました。この両者に意味的な違いはありません。
土地表題登記と建物表題登記
表題登記について、「土地表題登記」「建物表題登記」などという言い方がされることもありますが、これは正式名称ではなく、あくまで便宜的な言い方です。「土地表題登記=土地に対する表題登記」「建物表題登記=建物に対する表題登記」という形で、その登記が土地・建物のどちらに対するものなのかを分かりやすくするために、こういう言い方を使うケースもあるのです。
表題登記の申請期限
表題登記には申請期限が設けられています。原則として、土地や建物の所有権を得てから、1ヵ月以内に申請することが必要となります。これを守らず、登記しないまま放置してしまうと、不動産登記法第百六十四条に基づく罰則の適用対象となってしまい、10万円以下の過料が科せられる可能性が出てきます。
すでに申請期限が過ぎている場合は?
表題登記の申請期限は1ヵ月ですが、数年、あるいは数十年も建物が未登記になっていた、というケースは少なくありません。申請期限が過ぎているので過料が課せられる対象ではあるものの、実際には見過ごされて「過料の支払いについて特に何も言われなかったため、いつの間にか登記を忘れていた」という状態になることが多いのです。しかし、未登記のままで放置するのは法的に好ましい状態ではありません。たとえ1ヵ月の申請期限を過ぎても、建築確認書等の所有権を証明する書類を添えるなどして所定の申請手続きをすれば登記は可能ですので、未登記という事実に気が付いたらすぐに、表題登記の手続きをとるよう心がけましょう。
-
筆界特定とは何か
筆界特定とは、簡単に言えば「対象の土地の法的な境界がどこなのかを明確にさせる」というものです。「土地の境界なんてきちんと分かっているのが当然だ」と思う人も多いですが、実際には、古くからある土地などの場合は、境界が不明確・あいまいになっているケースも少なくないのです。この境界を明確にするための書類の作成や筆界標(境界標)を設置するのが、筆界特定の手続きとなります。
筆界と境界の違い
筆界と同じような意味を持つ言葉として挙げられるのが「境界」です。この2つの言葉には、「その言葉が示す範囲」に違いがあります。
境界には、「不動産登記法、つまり公法上に存在する境界で、登記によってしか変更することができない境界=筆界」と、「土地の所有権の範囲を示す私法上の境界で、所有者間の合意で変更可能な筆界=所有権界」の2種類があります。つまり「境界という大きな枠のひとつに、筆界がある」ということです。実際には、筆界と所有権界は一致するケースが大半を占めるので、「境界=筆界」と考えても、一般的にはあまり差しつかえないと考えても問題はありません。しかし、一部には「過去にお互いの話し合いで所有権の変更合意があったため所有権界は変更したが、登記の変更手続きはしておらず、筆界と所有権界が不一致となっている」といったケースも存在します。
筆界特定の必要性
筆界特定には「自分の土地の、公法上の境界を明確にする」という目的がありますが、この筆界特定の必要性はきわめて大きいと言えます。
たとえば、土地の売却をしたいと思っても、筆界があいまいなままだと、買い手に不安を与えてしまう要素があると見なされ、売却の条件的に不利になってしまうこともありますが、筆界特定ができている土地なら、そのような条件的不利をこうむらずに済みます。また、自分が土地を買う際も、筆界特定がされていない土地を選ぶと「あとから筆界について隣と認識が合わず、土地の権利の主張がぶつかってトラブルになるかもしれない」「建物を建てた際、気付かず隣の筆界にまで越境してしまうかもしれない」などというリスクがつきまといます。そうしたリスクを避けるためにも、筆界特定されている土地を選ぶこと、あるいは、現況で筆界特定がされていない土地に対して、購入前に筆界特定をしてもらうことを条件として業者と交渉することなどが大切です。
-
審査請求とは何か
審査請求とは、「不動産登記における、登記官の処分に対する不服申立て」です。たとえば「不動産登記の申請に行ったところ、登記官に却下されてしまった、申請の取り下げをするように言われた、納得できない」などといった時に、それに対する不服申し立てとして、審査請求をします。この審査請求の申請は、法務局長に直接出すのではなく、審査請求の対象である登記官を経由しなければなりません。つまり、登記官にとっては「自分がやった処分に対する不服に関する申請を、自分が受け取る」ということになります。そして登記官が、その審査請求には正当な理由があると認めた場合は、その件にきちんと対応する必要があり、逆に正当な理由がないと判断した時は、請求から3日以内に、登記官自身の意見をつけた上で、法務局または地方法務局の庁に送る、という手続きをとることになります。
審査請求から生じる賠償責任を負う先は?
審査請求をした結果、登記官の過失や故意などで損害をこうむったことが認められた場合、その賠償責任は国に生じることとなり、基本的に登記官個人が賠償責任を負うということはありません。ですが、登記官に重大な過失があった場合などは、国はその登記官に対して損害賠償の負担を求める求償権を持つことになります。
審査請求について、よくある勘違い
審査請求について、よくある勘違いとして挙げられるのが「登記の内容が間違っているから、審査請求をしたい」という考え方です。審査請求というのは、あくまで登記官の処分そのものに対する不服の申し立てであって、登記内容の間違いを指摘する、という趣旨のものではないのです。「申請の段階では正しい内容にしていたはずなのに、登記簿では建物の構造の表記が実際のものと違っていた」など、登記官のミスによって登記内容が事実と違った状態になっていた、などといった表記間違いに対しては、「実際の建物の状態に、登記内容を更正してもらう」という更正登記の手続きをとる形になります。その際、「〇年〇月〇日に、登記官の過誤につき、更正許可」という趣旨の記述が添えられます。
-
変更登記とは何か
変更登記とは、その名の通り「登記に書かれている内容を変更する」というものです。変更登記の種類としては、土地地目変更登記と建物表題変更登記(建物表示変更登記)があります。土地地目変更登記とは、田や畑、山林だった土地を宅地にした時や、宅地を駐車場に変えた場合など、土地の使用目的や用途に変更があった際に必要な手続きです。そして建物表題変更登記とは、すでに建って登記も済んでいる建物の状態や使用目的に変更があった際に必要な手続きです。たとえば「増改築で床面積が変わった」「居住用として使っていた家を、事業用の事務所として使うことにした」「リフォームで屋根の種類や、住宅の構造(木造から鉄骨へ、など)が変わった」「車庫を新たに建てた」などといった事例が、この建物表題変更登記が必要な事例として挙げられます。
農地転用の土地地目変更登記は要注意
土地地目変更登記の中で、特に注意すべき必要があるのが、田畑などの農地を宅地に変更する際の手続きです。農地には、農地法という法律が大きく関与しており、これによって売買に大きな制限がかけられているのです。この制限を解除するためには農業委員会に、農地を宅地などに転用するための許可書または届出書を出すことが必要となります。こうした手続きをせず、いきなり土地地目変更登記をしようとしても、法務局から農業委員会に許可書または届出書があったかどうかの照会がかかるため、一定期間は事務手続きが止められてしまいますので、先に農地転用に関する部分から取りかかることが必要です。
変更登記の申請期限
変更登記の申請期限は、不動産登記法によって、土地地目・建物表題ともに、「変更があった日から1ヵ月以内」と決められており、これを怠った場合、10万円以下の過料が課せられる可能性がある、とされています。しかし現実には、変更登記をしていないどころか未登記の物件も多く、さらに、それらに関して過料がかけられた事例も、現状ではまず見当たらないのが事実です。つまり、今のところは「仮に1ヵ月以上変更登記をせず放置したとしても、過料が課せられるリスクはきわめて低い」と言えます。しかし、当然のことながら、「実質的には過料が見過ごされている」という、この現状がいつまでも続くという保証は一切ないというのも事実です。ですから変更登記が必要な事例が発生した時や、変更登記を済ませていない事例があったと気付いた時は、いち早く申請のための対応をとるのが最善手と言えるでしょう。
-
土地地積更正登記とは何か
土地地積更正登記とは、「登記簿に記載されている土地の面積(公簿面積)と、測量等で判明した実際の土地の面積(実測面積)が違っていた場合に、正しい土地面積に登記簿記載を更正するという手続きのことです。「登記簿に記載されている土地面積は正確なものである」と思われがちですが、実際には違いが生じているケースも少なくありません。そして、土地地積更正登記については、不動産登記法において申告を義務付けるような記述がないため、更正登記をせず放置されている土地も少なくない、というのが実情です。しかし、公簿面積と実測面積に違いがあると、境界争いの原因となったり、土地の売買や相続などにおいても支障をきたすことがあるため、更正をしないまま放置するというのは得策ではありません。
古くからある土地は要注意
土地の公簿面積と実測面積が違う、という、土地地積更正登記が必要となりやすいケースとして挙げられるのが「古くからある土地」です。不動産登記の制度の大元となったのは、1873年(明治6年)に明治政府が行った地租改正です。地租(土地にかかる税金)を決めるために、全国で大々的に測量が行われました。ただ、当時の測量技術そのものは未熟で、しかも測量すべき件数が膨大であったことから素人による測量も多く、さらに「地租を軽くしたいがために、わざと土地面積を過小報告する」というケースもありました。こうした様々な要素が重なって、昔からある土地の公簿面積は、本当の土地面積である実測面積とはかけ離れたものになっている、というケースも少なくありません。
土地地積変更登記との違い
土地地積更正登記と混同されやすいものとして、土地地積変更登記が挙げられますが、土地地積更正登記が「当初から公簿面積と実測面積が不一致だった」という時に行われる手続きであるのに対し、土地地積変更登記は「河が氾濫した際に土地の一部が削られてしまい、土地面積が減ってしまった」など、自然現象によって土地の面積が変わってしまう現象が起こった際にとる手続きである、という違いがあります。また、不動産登記法において、土地地積更正登記については前述の通り申告義務の規定はないのですが、土地地積変更登記については、変更が生じた日から1ヵ月以内の申請が義務付けられていますので注意が必要です。
-
土地合筆登記とは何か
土地合筆登記とは、隣接している数筆(いくつかの区画)の土地を、法的に一筆(一区画)に合体させるための登記手続きです。数筆に分かれた土地をひとまとめにして売却したい場合などに、この手続きを利用します。合筆がなされた場合、その土地の地番は、合筆した土地の地番の中で一番若い地番があてられます。たとえば、「123番地と124番地を合筆した場合、合筆後は123番地となる」「3番地1と3番地2を合筆した場合は、合筆後は3番地1となる」という形です。この場合124番地は閉鎖され、再使用されることは、まずありません。ちなみに、地番のつけ方は法的に定められているため「せっかく合筆するなら好きな地番を指定したい」といった要望があっても、応じてはもらえません。
合筆できない土地もある
土地合筆登記は、かなり制約が多い登記でもあります。「すぐ近くにあるものの、隣接しているわけではなく、少し離れている」「隣接しているが、宅地と雑種地など、地目が違う」「隣接しているが、1丁目の土地と2丁目の土地という形で、地番の区域が違う」「隣接しているが、それぞれの土地の所有者が違う」「隣接していて所有者も同じだが、複数の所有者が居て、持ち分の割合が土地ごとに違う」「隣接していて所有者も同じだが、所有権の登記をしている土地としていない土地がある」などといったケースは全て、土地合筆登記ができません。また、抵当権や質権など、所有権以外の権利登記がついている土地についても、合筆には大きな制限があります。「土地が隣接しており、所有権以外の権利登記の内容も全て同一」など、一定の条件をクリアすれば合筆可能なケースもありますが、条件自体が非常に厳しいこともあり「所有権以外の権利登記がある土地の合筆はきわめて難しい」というのが現実です。
土地合筆登記はハードルが高い
土地合筆登記は、先に挙げた「最低限の制限」だけでも、素人にとっては分かりにくく、判断が難しい部分もあります。さらに、法務局での登記記録や地積測量図、隣地関係などの調査なども必要であることを考えると、土地合筆登記は、素人にとってかなりハードルが高い不動産登記であると言えます。
-
土地分筆登記とは何か
土地分筆登記とは、一筆(一区画)の土地を、法的に数筆(いくつかの区画)に分けるための登記手続きです。「土地の一部だけを売りたい」「遺産として土地を相続したが、相続人が複数いるので土地を分けたい」「一筆の土地に複数の所有者が登記されているため、持ち分に応じて土地の分割をしたい」「融資を受けるために土地を担保にするが、土地のすべてを担保にしたくはないので、融資に見合った分だけの土地を分筆し、その分筆した土地だけに担保をつけたい」「土地が大きくて固定資産税が高いので、固定資産税が節約できるよう調整して土地分割したい」などという時に、この手続きを行います。ちなみに分筆後の地番は、枝番がつくのが一般的です。たとえば123番地の土地を2筆に分筆した場合は、123番地1、123番地2という形で分筆されます。
土地分筆登記で特に注意すべきケースとは
土地分筆登記を、固定資産税節税のために行う、という人もいますが、これには細心の注意が必要です。なぜなら、固定資産税は分筆後の土地の面積だけでなく、間口・形状なども考慮して決められるので「土地を分筆すれば、必ず固定資産税が安くなるとは限らない」という理由があるからです。また、分筆によって、いわゆる「旗竿地」ができる場合、その間口が狭すぎる場合などは建築基準法違反となり、家を建てることが認められず、土地の価値そのものが大幅に下落してしまうというケースもあります。「旗竿地にすれば固定資産税が安くなるだろう」などと安易に考えてしまうのは禁物です。
相続による分筆にも要注意
相続による分筆にも、注意が必要です。というのも、相続による分筆は「相続割合に応じて、土地の面積を単純に割って相続すればいい」というものではないからです。角地や大通りに面した土地は同じ面積でも評価が高くなりますし、そうでない土地は評価が低くなりますので、こうした面積以外の部分も考慮する必要があります。そのため、まず境界確定測量をしてもらい、そこから遺産分割協議書で「どの部分を誰が相続するのか」を、評価額等も考慮した上で決め、そこから分筆登記をした上で、相続登記も完了させる、という何段階もの手続きを踏む必要があります。
-
建物合併登記とは何か
建物合併登記とは、現状では別個の独立した建物として登記されている複数の建物を、ひとつの建物として登記することを指します。たとえば「母屋と離れがそれぞれ別の建物として登記されているが、これをひとまとめにしたい」という時などにこの手続きを行います。このケースの場合、建物がそれぞれ別個で登記されている段階では、母屋も離れも「主たる建物」という扱いとなりますが、建物合併登記がなされた後は、母屋が主たる建物で、離れが附属建物となり、「主たる建物と附属建物をひっくるめて、ひとつの建物」という扱いとなるのです。他にも「店舗と居宅を合併する」「事務所と物置を合併する」などといったケースに、この建物合併登記が利用できます。建物合併登記の申請期限というのは特にありません。なぜなら、建物合併登記は「建物自体に変更を加えるのではなく、あくまで登記上で、ひとつの建物として登録する」という性質のものであるため、申請がなければ、そもそも何も変わることがない、という理由があるからです。
建物合併登記にかけられている制限
建物合併登記は、「どんな建物でも合併できる」というわけではなく、不動産登記法による制限がいくつかあります。たとえば、建物の所有者が違う場合や、「一方が所有権登記ありで、もう一方が所有権登記なし」などという所有権登記の有無の違いがある場合や、「抵当権のついている建物とついていない建物がある」など、権利登記の違いがある建物の合併も認められません。そして、「複数の貸家を合併したい」というケースも、建物合併登記はできません。その理由としては、母屋と離れのように「どっちが主で、どっちが附属か」が明確にされているケースとは異なり、それぞれが独立利用されているという理由で、主たる建物と附属建物に分けることできない、という事情が挙げられます。
建物合体登記との違い
建物合併登記と混同されやすい登記として、建物合体登記というのが挙げられますが、建物合併登記と建物合体登記の最大の違いは「建物はそのまま変更なしの状態にするか、変更を加えて物理的にひとつの構造の建物として仕上げるか」という点です。建物に手を加えることなく、登記上だけひとつの建物扱いをしたい場合は建物合併登記を、建物に手を加えて実際の建物構造をひとつにする場合は建物合体登記をする、という形になります。
-
建物合体登記とは何か
建物合体登記とは、2戸~数戸の独立した建物に、増築や隔壁の除去など物理的な変更を加えて、構造そのものをひとつの建物へと変更した際に行う登記です。この登記手続きでは、表題登記が変更されるのではなく、合体前の建物の表題登記はすべて抹消され、合体後の建物を新たに表題登記する、という流れになります。ただし、合体する建物が主たる建物同士ではなく、主たる建物と附属建物であった場合は、建物合体登記をするのではなく、建物の表題部の変更登記を行います。
建物合体登記の様々なケース
建物合体登記は、比較的制限が少ない登記です。たとえば、未登記の建物同士の合併や、一方が未登記でもう一方が登記済みであるケース、さらには建物の所有者が異なるケースなどでも、建物合体登記の手続きは可能となります。ですが、所有者が異なる合体登記の場合、合体後は持分所有となりますが、トラブル等を防ぐために、その持分割合を事前にじゅうぶん協議して決めておく必要があります。また、建物合体登記は、制限が少ない分、様々なパターンがあり、その数多くのパターンの中から自分のケースに該当するものを間違いなく探し、その手続きもぬかりなくこなすというのは、個人ではかなり難しい部分もある、というのが事実です。
建物合併登記との違い
建物合体登記と、建物合併登記の大きな違いは「対象の建物に物理的な変更を加えるかどうか」です。建物合体登記は、離れていた部分に増築を加えるなどして、実際の構造をひとつの建物に変える際に行う登記です。これに対して建物合併登記は、建物には物理的な変更を加えず、「建物はそのままで、登記上でひとまとめの扱いにする」という趣旨の登記となっています。また、両者の違いはこれだけではありません。建物合体登記は、合体前の建物の所有者が別々でも認められ、合体後に所有者ごとの持ち分が記載されるという形になりますが、建物合併登記は所有者が違う建物では認められません。また、申請期限についても、両者には大きな違いがあります。建物合併登記は「そもそも申請がなければ、何も変わることがない」という理由で、申請したい時にすれば良い、という性質のものですが、これに対して建物合体登記は、建物の合体から1ヵ月後が申請期限となっており、申請を怠ってこの期限を過ぎると、10万円以下の過料が課せられる可能性も出てきます。
-
建物分割登記とは何か
建物分割登記とは、「主たる建物と附属建物で、不動産登記上でひとつの建物扱いになっているものを分割し、それぞれ独立した主たる建物として登記する」などという際に行う手続きです。「母屋を主たる建物、離れを附属建物として登記していたが、離れも主たる建物扱いに変更したい」という場合などに、建物分割登記の手続きを行います。また、建物分割登記は「全ての建物をひとつずつ分割する」とは限らず、例えば「主たる建物である居宅に対して、事務所と物置の2つが附属建物としてついている」という場合、居宅と事務所をそれぞれ主たる建物にして、物置は居宅の附属建物のままにしておく、といったパターンの分割をすることも可能です。
建物分割登記が必要なケースとは
建物分割登記が必要なケースとしては、まず「物件を担保に入れる(抵当権を設定する)」というのが挙げられます。「主たる建物である居宅だけを担保にしたい」という場合に、この建物分割登記をすれば、他の建物には抵当権は設定されずに済みます。ただし、抵当権の設定というのは、大抵は土地にもかかってきますので、建物分割登記をする際は、土地の分筆登記もしておくことがおすすめです。また、相続によって建物を分ける場合や、「附属建物だけ生前贈与したい」「主たる建物を売却して附属建物は残したい」などといったケースも、建物分割登記が必要となってきます。
建物分割登記の申請期限
建物分割登記に、定められた申請期限というものはありません。なぜなら、建物分割登記というのは、実際に「ひとつの建物を2つに物理的に分離する」というものではなく、建物そのものにはいっさい手を加えないからです。「申請しなければ、登記上での分割もされないまま」という結果になるだけなので、建物分割登記は「分割したいと思った時に申請すべきもの」という扱いとなります。
-
区分建物表題登記とは何か
区分建物表題登記とは、マンションなどの区分建物一棟のうち一部を、「区分所有」として個別に所有できるようにするために必要不可欠な登記で、この区分建物表題登記によって、ひとつひとつの住戸ごとに登記簿が作られます。たとえば普通の戸建てなら、一階と二階で所有権を別にすることはできませんが、マンションなどの区分建物なら、この区分建物表題登記をすればそれが可能とになるのです。ちなみに、その区分建物の敷地権(土地の権利)については、その区分建物の登記簿に記載されます。
区分建物表題登記は個人ではできない?
区分建物表題登記は、「マンションを買ったから、自分でこの登記をしたい」と思っても、できるものではありません。なぜなら、その区分建物に対する区分建物表題登記は、その建物内の全ての住戸に対して、一括して登記を行う必要があるからです。「一棟まるごと買う」というようなことでもしない限りは、マンション購入者個人が区分建物表題登記の手続きをすることはできません。そのマンションを販売している不動産会社などが、区分建物表題登記を土地家屋調査士に依頼する形となります。
建物区分登記との違い
区分建物表題登記と似た名前の登記として、建物区分登記というものがありますが、両者には大きな違いがあります。区分建物表題登記は、新築のアパートやマンションなどが対象で、「最初から、区分建物としての登記をする」というものですが、これに対して建物区分登記というのは「すでに建っている中古の一棟の建物(ひとつの建物として登記され、現状では区分建物扱いにはなっていないもの)を、区分建物にするための登記、となります。つまり「最初から区分建物にするなら区分建物表題登記をして、途中から区分建物にするなら建物区分登記をする」ということになります。
-
建物区分登記とは何か
建物区分登記とは、「区分建物としての要件を満たしながらも、ひとつの建物として登記されているものを、分割するための登記」です。区分建物としての要件とは、「住戸ごとに、構造的な独立性と、利用上での独立性の両方を満たしていること」です。構造的な独立性とは、壁・床・天井などによって他の区分としっかり仕切られているかを指し、利用上での独立性とは、その区分だけで独立して利用できるかどうかを指します。こうした条件を満たすマンションやアパートなどは、まさに「区分建物の代表的な存在」と言えます。
建物区分登記をする事例としては、「今まで一人のオーナーが一括して管理していた賃貸マンションを分譲マンションに切り替えたい」という場合や、一棟のマンションのオーナーをしている人が、一部の区分だけ売却したい、あるいは一部の区分に抵当権を設定したい、などといったものが挙げられます。建物区分登記が完了すれば、住戸ひとつひとつに登記簿が作られるため、住戸ごとの売買や抵当権設定・相続などができるようになります。
建物区分登記ができない建物
建物区分登記は、どんな建物でも対象になる、というわけではありません。たとえば一般的な戸建て住宅は、「各部屋が構造的に独立しており、利用性についても、各部屋単独で問題なく利用できる」というわけではないので、「1階と2階を建物区分登記によって分ける」ということは認められません。ただし、親世帯と子世帯でそれぞれ独立して利用できる二世帯住宅や、「新たに間仕切りを作った上で設備も見直し、独立して利用できる空間を作った」などという場合は、建物区分登記をすることが可能となります。
区分建物表題登記との違い
建物区分登記と似た名前で混同されやすいのが、区分建物表題登記ですが、区分建物表題登記の性質は、建物区分登記とはかなり違います。建物区分登記は、「すでにある建物を、区分建物として個別に扱えるよう切り替えるための登記」で、中古の建物が対象となり、その建物の所有者であれば、個人で建物区分登記の手続きをすることも可能です。これに対して、区分建物表題登記は、最初(新築時)から区分建物としての登記をしたい場合に行うもので、「マンション等の新築時に、一棟の区分建物内にあるすべての住戸を一括して登記する」ということが必要です。一括登記という性質上、新築一棟買いでもしない限りは、個人が手続きできるものではなく、基本的には販売不動産会社が土地家屋調査士に依頼して行う形になります。
-
建物滅失登記とは何か
建物滅失登記とは、建物に関する登記を閉鎖する手続きのことです。対象となる建物を解体して、建物が無くなった場合、そのまま放置しておくと「登記内容(建物がある)と事実(建物はもう存在しない)に食い違いが出てしまう」という形になってしまうため、この申請をすることが義務付けられています。
建物滅失登記をしないとどうなる?
建物を解体しても、建物滅失登記をしなかった場合の問題点としては、登記上では建物が存在したままの状態になっているため「解体して、実際には存在しない建物に対して、固定資産税がかかる」という事態が発生する、ということが挙げられます。また、更地となった土地を売却しようとする際や、その土地を担保にお金を借りる場合などは、登記内容と事実が食い違ったままでは、不動産業者や金融機関はまず応じてくれないため、建物滅失登記が必要となるのですが、これが解体後の年数がたてばたつほど、必要書類の入手に支障をきたすリスクが高くなってしまいます。
また、近年では「建物滅失登記をしなかったとしても、市町村側が現地調査によって、建物の解体に気付く」というケースも増えています。この現地調査は、おおむね10月ごろから行われ、この調査によって建物滅失登記の申請を速やかに行うよう要請されることもあります。また、仮に市町村側の現地調査で気付かれなかったとしても、そもそも建物滅失登記は、解体後1ヵ月以内での申請が必要であることが不動産登記法で定められており、これを怠った場合は10万円以下の過料が課せられる可能性も出てきますので、「市町村にばれなければいい」という考えは慎むべきです。
居宅は空き家にしておいた方が得?
建物滅失登記をしないままだと、建物に対する固定資産税はかかりますが、その建物が居宅である場合は、「建物滅失登記後は、土地に対する固定資産税が高くなる」という状態になります。なぜなら、居宅が建っている土地に対しては、固定資産税と都市計画税の優遇措置がとられているからです。更地にして建物滅失登記をした場合、この優遇措置が適用されなくなるのです。とはいえ、「解体したのに、優遇措置を受け続けることを目的に建物滅失登記をしないまま放置する」というのは、節税目的で故意に解体の事実を隠した悪質な行為と見なされてしまうリスクもあります。ですからこの場合は、空き家状態であっても、次の買い手が見つかるまで建物は残したままにしておく、という手を使うことの方が多いです。
しかし、この空き家に対しても、平成26年11月に公布・平成27年2月施行の「空家等対策の推進に関する特別措置法」というものがあり、衛生上の問題や倒壊の危険性を抱えていると判断された空き家に対しては優遇措置を無くす、という流れになっています。「空き家状態になってからすぐに土地を売りに出しているので、買い手がつくのは時間の問題」という状態なら当面は空き家を残しておいても構いません。しかし、長年空き家のままで放置するとなると、この特別措置法の影響を受ける可能性が高くなりますし、近隣にも迷惑をかけてしまうこととなるため、解体と建物滅失登記をした方が好ましいと言えます。
-
民間紛争解決手続とは
土地家屋調査士の中でも、「ADR認定土地家屋調査士」に認定されている者は、土地の筆界(境界)に関する民間紛争解決手続(ADR)の代理手続業務を行うことができます。「土地の筆界が不明確であることが原因で、お隣と揉めている」などというケースでは、かつては裁判で決着をつけるしかない、という状況でした。しかし、平成16年12月公布・平成19年4月施行の「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)」によって、訴訟する前にまず、公正な第三者の関与によって、民事上の紛争を解決する、という制度ができたのです。この代理業務を引き受けるのが、土地家屋調査士会が運営する「境界問題相談センター」で、ADR認定土地家屋調査士や弁護士を調停人としての、紛争解決のための話し合い、その手続きについてのサポートをしてくれます。そして無事調停合意ができれば、その合意内容をもとに、境界標の埋設や登記手続を行うという流れになります。
ADR認定土地家屋調査士とは
ADR認定土地家屋調査士とは、土地家屋調査士の中でも、「土地家屋調査士会が実施する特別研修を受講して研修後の考査に合格し、なおかつ、法務大臣の認定を受けた者」だけが名乗れる、いわば「民事紛争解決手続きの代理業務もこなせる特別な土地家屋調査士」です。ADR認定土地家屋調査士は、民事紛争に関する知識を豊富に有しているため、「実際にはまだ紛争すら起こっていない、普通の不動産登記」であっても、将来的な紛争のリスクを予想し、それを予防・回避するためにどうすればいいかということも考えられる、などの強みがあり、より信頼感が高い存在と言えます。
筆界に関する紛争が起こったら
筆界(境界)に関する紛争の当事者となってしまった場合は、先ほど紹介した「境界問題相談センター」に相談してみることをおすすめします。境界相談センターは全国各地にありますので、まずは電話で、相談したい旨を連絡します。センターが相談を預かると、その内容をADR土地家屋調査士や弁護士が整理した上で、取り扱える案件かどうかを判断し、取り扱えると判断した場合は、いよいよ本格的な相談、そして調停の手続きを進めていくという流れになります。また、センターが無料相談会を開催していることもありますので、最初はそれを利用してみるというのもおすすめです。